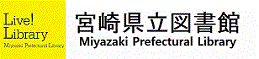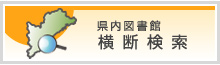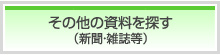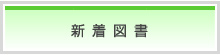4月、学校にも巷にも、希望に満ちた初々しい新入生の溢れる季節である。ランドセルが歩いているような微笑ましい1年生の登校姿を目にすると、これからさまざまな事が起こるであろう長い人生を、元気に、事故なく、すくすくと育ってほしいと念じ“がんばれよ”と、つい声が出そうになる。
以前、職場の先輩の方が、酒を酌み交わしながら楽しそうに話されたことがある。「この春から息子が学校に通い始める。息子にとっては初めての通学路である。今日は、この息子と一緒にその道をゆっくり歩き、信号の位置や道路の様子、横断歩道の渡り方等を教えてきた。」と、子どもさんの成長を喜び、実に嬉しそうであった。あれから、30年余り時は経過し、その子どもさんも今は立派な父親のはずであるが、今度はお孫さんの成長を子どもさんと共に見守っておられることだろうか。
ところで、当時、私は高校1年生の担任であった。高校生と言っても新入生はまだあどけなく、中学生の雰囲気を多く漂わせていた。その中に、A君がいた。話しかけると、明るい反応が響きよい言葉と共に直ぐに返ってくる。級友とのコミュニケーションもスムーズで、会話がよどむことがなかった。どうしたら、このようなコミュニケーション能力は育つのか、いつも脳裏の隅にあった。
A君宅への家庭訪問の折り、その疑問についてお尋ねした。お母さんは、「この子が小さい時、周りに興味を持ち色々な問い掛けを発すると、それにできるだけ丁寧に答えてきました。発電所についての疑問を持ってくれば、実際に発電所に連れて行き、それを丁寧に説明しました。」等々、話してくださった。まさに、正法に不思議なしである。
その時以来、私はPTAの会合等でよくこの事例を引いて、子育て時の“

啄同時”のこと、即ち適時性の大切さを話題にさせていただいた。子どもが真に親に頼り、親の力を欲しようとするその時期に、しっかりと子どもに応え、教えるべきはしっかりと教え、子どもと共に過ごす時間がいかに大切かを、また、その時なくして、高校生である我が子に絆の深さを要求することがいかに難しいかを、お話ししたことでした。
今の季節、総合文化公園は桜花の時でもある。我が子と共に、孫と共に県立図書館周辺の散策をされる方も多いかと思う。この公園には、郷土の偉大な先人の銅像もある。安井息軒、高木兼寛、若山牧水、石井十次、川越進などの方々の銅像を巡り、子や孫と共に先人の遺徳を偲び、その時代に思いを馳せ、その業績を顕彰する一時もまた、得るものが多いと思う。県立図書館には資料もたくさん揃えてある。
今年は、完全学校週五日制もスタートした。